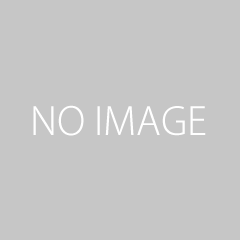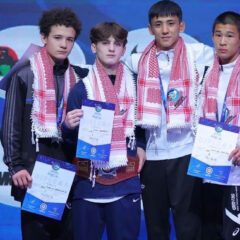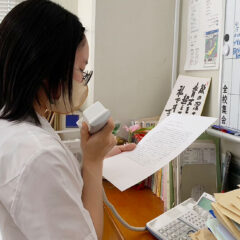週間モビ工第15回:オープンスクールのお知らせ
2020年4月新自動車実習棟が完成
新自動車実習棟の魅力を週1で紹介!「週間モビ工(こう)」!モビリティ工学科のや二級自動車整備士課程の自動車専攻科の先生たちが施設や実習風景を紹介していきます!
NO.1:実習棟前景 / NO.2:電気自動車充電設備 / NO.3:自動車エンジン / NO.4:外部講師による講義
NO.5:クレーン業務特別教育 / NO.6:小型エンジンの分解組立 / NO.7:計算技術検定取得 / NO.8:部品の精度判定実習
NO.9:エンジンの燃料供給システムの理解 / NO.10:シャシ整備応用実習 / NO.11:ブレーキ点検実習
NO.12:エンジンの分解組立 / NO.13:ロータリ・エンジンの分解組立実習 / NO.14:就職説明会 / NO.15:オープンスクールのお知らせ
■モビリティ工学科 小坂先生
モビリティ工学科では、8月5日・6日のオープンスクールに向けて準備を進めています。自動車メーカー及び陸上自衛隊からご協力頂き、スポーツカー、自動運転車、大型トラック(調整中)、陸上自衛隊車両を展示する予定です。中学生の皆さん、いろんな車両を見て、興味を深めて下さいね。お待ちしてます。
真剣に説明を聞いています。
■自動車専攻科 川島先生
専攻科1年生に対し、県内の自動車ディーラーによる就職説明会が実施されました。説明会では、企業の概要や、職種(エンジニア)や給与、福利厚生等の他、「企業の求める人材」の話を伺うことができ、生徒たちにとっても今後の教育・実習での努力の方向性の参考となりました。
■設備・用語説明
「就職説明会」
自動車専攻科では、昨年度も卒業生全員が二級自動車整備士資格に合格しており、高い合格率を誇っています。二級自動車整備士は自分で整備工場を設立することも可能な資格で、自動車に関する仕事に大きく、自動車業界に就職していくうえで大きな強みとなり、結果として全国の自動車関連企業から多くの求人があります。今年度の就職説明会については、新型コロナウイルスの状況を見ながら、県内外の企業と現在調整中です。
また、本科は、高校卒業以上の方であれば他校からでも入学できますので、自動車業界を進路に考えている方はぜひ自動車専攻科へ!資格を取得して、全国の自動車業界に羽ばたきませんか。
ここ3年間(平成29年度卒~令和元年度卒)の卒業生の進路状況
●県内
トヨタカローラ宮崎(株)、宮崎トヨタ自動車(株)、宮崎トヨペット(株)
ネッツトヨタ宮崎(株)、(株)スズキ自販宮崎、宮崎ダイハツ販売(株)
宮崎県自動車整備振興会
●県外
UDトラックス(株)、いすゞ自動車九州(株)、南九州日野自動車(株)
大阪トヨタ自動車(株)、(株)GST、神奈川トヨタ(株)、
ネッツトヨタ神奈川(株)、富士スバル(株)、トヨタカローラ神奈川(株)
福岡スバル(株)、福岡トヨタ自動車(株)、ネットトヨタ福岡(株)
(株)ホンダ四輪販売南九州、(株)南九州マツダ、南九州スバル(株)本社
ネッツトヨタ鹿児島(株)、太陽建機レンタル(株)、ハーレーダビッドソン大阪
YSP国分
ロータリーエンジンを使った実習中です。
■自動車専攻科 福元先生
エンジンには、直列4気筒、直列6気筒、V型6気筒、水平対向、ロータリなど多くの種類があります。専攻科では、多種類のエンジン分解組み立て実習を行い構造や特徴を理解しています。今回の実習では、初めて見るロータやエンジンの構造に目を輝かせています。
ご要望があれば、いつでも出前授業にお伺いいたしますので、お気軽にご連絡ください。
■設備・用語説明
「ロータリー・エンジン」
ロータリ・エンジンはマツダ自動車が世界で唯一量産化に成功した画期的なエンジンで、燃料を燃焼させて、おむすび型のロータが回転することで、出力を取り出しています。
通常のレシプロ・エンジン(往復運動)と違いロータリ・エンジンは回転運動なのでエンジンの振動が少なく、部品も少なく、小型で軽量でありながら高出力を得られるエンジンです。
世界初の実用・量産化ロータリーエンジンを搭載した車は、皆さんご存知の日本企業「マツダ」が1967年発売したコスモ・スポーツです。その後も、ルーチェ、サバンナ、FX-7(FC型)、RX-7(FD型)、RX-8などに搭載されました。なんと一時期マツダパークウェイというバスにも搭載されたこともあります。
8月5、6日にあるオープンスクールでロータリーエンジンの実物を見ることができます!是非、オープンスクールに参加してみませんか?
詳しくはオープンスクールのページをチェックしてみてください!https://oubi.ed.jp/edco/product/オープンスクール2020/
バルブリフターを使ってバルブを外す様子
■モビリティ工学科 小坂先生
三級整備士養成課程である高校3年間では、1、2年生共に同様の実習を実施します。早めから整備に触れることで、2年次での整備士資格合格を目指しています。1学期はエンジンの分解・組立を主に行っており、写真ではバルブリフターを使い、バルブを外そうとしている場面です。全てを分解したら、逆の手順で組立を実施し、構造・原理を理解し、工具の使い方に慣れます。
■設備・用語説明
「レシプロエンジンの構造とは?」
エンジンはどのようにしてエネルギーを作り出し車を動かしているのでしょう?自動車はもちろん、船舶も飛行機も同じですが、燃料を爆発させ、その圧力を動力に変えるのがエンジンの仕組みになります。
その方式でも、飛行機や高速客船はガスタービンエンジン、自動車や、一般的な船はレシプロエンジンを採用していることが多いです。「エンジン」と思い浮かべてぱっと想像するのが、レシプロエンジン(ピストンエンジン)です。
モビリティ工学科は主にレシプロエンジンの分解組立を行なっています。手順としては、ヘッドカバーをはずし、タイミングベルト、ギヤ、カムシャフトなどを順番に取り外します。重量のあるシリンダーヘッドの取り外しは注意しながら行います。外した部品は、組立する時にわかりやすいように順番に作業台に並べていきます。続いてエンジンを90度回転させ、オイルストレーナー、ピストンを取り外していきます。
ピストンはガソリンが爆発するエネルギーを受けて高速で上下に動き、自動車を動かす原動力になる大事なパーツです。
組立作業は、分解した時と逆の順番で取り付けていきます。ボルトやネジは締め付けすぎると折れてしまうので、トルクレンチを用いて、指定された力で絞めていきます。
難しいように聞こえますが、実際に見てみるとシンプルで「なるほど」!となるような仕組みです、是非8月5、6日にあるオープンスクールで触れて見ませんか?
詳しくはオープンスクールのページをチェックしてみてください!https://oubi.ed.jp/edco/product/オープンスクール2020/
前輪を外してブレーキ点検をする様子
■自動車専攻科 日高先生
自動車で重要な部位である、ブレーキ関係は重点的に学習を行います。
ブレーキは、車輪と一緒に回転するブレーキローター(ディスク)をブレーキパッドを押し付けけ、その摩擦力を利用して車の減速や停止を行います。ブレーキの異常は事故に直結します。
高校生、中学生が良く利用する自転車も同様に摩擦力を利用して減速等を行っていますので、普段からしっかりと点検整備を行うようにしましょう。
■設備・用語説明
「ディスクブレーキ(制動装置)」
「安全の基本は止まること」です。この事を実現するために様々なブレーキの種類があり、自動車では主にディスクブレーキとドラムブレーキの2種類があります。
自動車のフロント側に採用されることの多いディスクブレーキは、車輪とともに回転する円盤状のブレーキローターを、ブレーキキャリパーという両側から挟み込むためのパーツを介してブレーキパッドを押し付け減速・停止します。
ディスクブレーキもドラムブレーキどちらも、回転エネルギーを、摩擦による熱エネルギーに変換して減速する構造ですが、熱を持ちすぎることや、摩擦による素材の摩耗がブレーキの「効き」にかかわってきます。長い下り坂で頻繁にブレーキを踏むと熱の発生が多くなったり、数年にわたって距離を走っていればブレーキパッドが摩耗します。
ブレーキの効かない自転車や自動車を想像しただけで乗るのが怖いですね。定期的に点検・整備を行いして、安全な自転車や自動車に乗りましょう。
■自動車専攻科 西留先生
本校最終学年である自動車専攻科2年生は、シャシ整備の応用実習を学んでいます。現在は、自動車をリフトアップし、本体からミッション(変速機)やエアコン装置を取り外し、点検後また取り付けるという実習を実施しています。
■設備・用語説明
「ミッション(変速機)」
エンジンの動力をタイヤに伝える動力伝達装置の一部です。最近の自動車は、95%以上がオートマチックを使用しているため、実習では、数種類のミッション取り外しや取り付けの作業を実施しています。
「エアコン装置」
自動車の冷暖房装置のことで、自動車の室内からエンジンルームまで多くの部品で構成されており、最終的にクーラーガスを充填して確認作業まで行っています。
「シャシ整備」
シャシ整備とは、自動車のエンジン以外の全ての整備に該当します。既に専攻科2年生は、各自動車ディーラーや整備工場に全員が内定決定しており、就職後に即実践できるように、実車を使い次年度からの整備士としての訓練を行っています。
■自動車専攻科 川島先生
現在、自動車専攻科1年生は、様々なエンジンを分解し、構造や作動の仕組みを学んでいます。分解した部品は精密測定機器を使い、その部品が使えるか否かの判定を行っています。毎日、千分の一の数字と向き合いながら和気あいあいと実習に取り組んでいます。
■設備・用語説明
精密測定機器
ガソリンエンジンやディーゼルエンジンを搭載した自動車は、約2~3万点の部品で構成され、その約半数近くをエンジンの部品が占めています。そのような自動車に使われる部品は、その一つ一つが高い技術と精度で製作されています。
言い方を変えると、普段皆さんが乗っている自動車は、その技術と部品精度に支えられて普通に走れて、曲がって、止まることができるようになります。
各部品の精度を測定するために必要な測定機器はたくさんありますが、エンジンの整備では、マイクロメータ、シリンダゲージ、マイクロメータなどの機器を使用します。
精密部品の集合体である自動車を整備し、お客様に安全と安心を届けることが、自動車整備士の仕事です。
■モビリティ工学科 難波先生
モビ工では、計算技術検定3級の取得を目指しています。機械や自動車には関数を使った計算が必要な場面もあり、その計算に「関数電卓」を使用します。合格に向けて、電卓を正確に使いこなせる能力を鍛えます。
■設備・用語説明
計算技術検定
計算技術検定とは、全国工業高等学校長協会が定める検定の一つです。
あまり聞き馴染みが無いかもしれませんが、工業数理基礎という授業の中で、資格取得に取り組んでいます。
工業数理基礎ってなに・・・?と思うかもしれませんが、具体的に、面積や体積、オームの法則など、小学校~中学校で習った数学に少しだけ物理をプラスしたものだと思ってください!
難しそうと思うかもしれませんが、「関数電卓」の使い方を覚えると難しめの計算でも自動で簡単に解けますので安心して下さい!しっかりと使いこなせるようになるように指導を行います。
また、本科では、他にも色々な資格取得にチャレンジしてもらいスキルアップを目指せます。将来、都城東に教員として戻ってきてくれる生徒が出てきたらという気持ちも持ちながらモビ工の先生全員が優しく面白く指導にあたっています。
【モビリティ工学科 岩下先生】
入学当初(整備士課程当初)から、小型エンジン教材の分解・組立の実習を行います。タイミングチェーン、シリンダヘッド、ピストン、クランクシャフト、バルブ、カムシャフトなどエンジンを構成する部品に触れながら構造や原理を学びます。
■設備・用語説明
小型エンジン教材
本科では、主にKFエンジンを教材として使っており、宮崎ダイハツ販売株式会社様より寄贈を受けたものです。水冷直列3気筒DOHC12バルブ658ccの軽自動車用エンジンで、ダイハツ工業が生産しています。搭載している車は、平成17年式以降のダイハツタント、ミラ、ムーブのほか、スバルのシフォン等にも搭載されています。
これらの車を街中でみかけた時は、モビ工の実習に使われているエンジンが搭載されている車だ!と思ってください!
【モビリティ工学科 田中先生】
本校、モビリティ工学科では多くの資格試験を受験します。その中のでも各学年を通して令和2年度初めてとなりますクレーン業務特別教育の実習風景です。みんな安全作業を心掛け真剣に取り組んでいます。
■設備・用語説明
クレーン業務特別教育
クレーン業務特別教育とは、エンジンや鉄骨など人の手では運べない物の移動に必要となる資格です。本校では、安全な取扱いなどを中心に実習を行っています。
この他にも、実務に関わる様々な資格を取得することができます。詳しくは、学科・コースのモビリティ工学科のページをご覧ください!
講義の様子
【モビリティ工学科 大浦先生】
モビリティ工学科では、年に複数回外部講師の方を招いて、より専門的なことを学ぶ機会があります。先月は最近話題の「自動運転の未来」というテーマで講義して頂きました。手放しで運転できる自動車の登場はもうすぐそこかもしれませんね!
■設備・用語説明
自動運転
私たちが何もしなくても目的地まで自動で走ってくれる自動車の自動運転。自動車に関心ない人にとっても想像・イメージし易い未来の理想の車ですね。現在、自動運転車が、徐々に現実のものになろうとしています。今のレベルは高速道路上などの限られた道路で、車線の維持、前走車と車間を維持しながら走る自動機能を持った自動車ができています。
【モビリティ工学科 細屋先生】
実習場には大小いろんなエンジンがあります。
入学したらまず、整備に必要な工具の名称、使い方を学び、段階的に小さなエンジンから分解・組み立てを繰り返し行い、構造・原理等を学びます。
■設備・用語説明
日野自動車製 N04C-UM ディーゼル(軽油)エンジン
OHV(シングルカム)4リッター 4サイクル水冷直列4気筒ターボ
出力:85kW(116馬力)/2500rpm 燃費10.40km/L
N04Cエンジンは普段よく見かけるトラックの日野デュトロやトヨタダイナなどに使用されています。
本校では、このエンジンの他にも、各社の乗用車用エンジンなどがあり、仕事に必要な実務能力を学ぶことができます。
お食事タイム(充電中)
【モビリティ工学科&専攻科 総括 福元先生】
新実習棟には、電気自動車(EV)の教育にも対応できるように、充電設備が2カ所設置してあります。最近では完全充電で450kmは走行できるようになりました。燃料タンクの代わりがバッテリーなので燃費ではなく、電費(でんぴ)と言います。モビリティ工学科で電気自動車の静かさと、加速力を体験してみませんか。お待ちしています。
■設備・用語説明
電気自動車(EV)充電設備
本校のEV充電設備は単相200Vで3kWの充電能力を持っており、実習で使う電気自動車の充電を賄っています。
経済産業省が2019年6月に発表した資料によると、電気自動車の普及率を2030年で全自動車の30%と予想しており、EV充電設備が高速道路のサービスエリアやコンビニエンスストアなどで気軽に利用できるようになる時代はそう遠くありません。
モビリティ工学科では、電気自動車やガソリン車以外の移動手段の時代が来ることを念頭に、バッテリーの取扱いや、電気自動車ならではのカリキュラムを多く編成しています。
【モビリティ工学科学科長 小坂先生】
皆さん、都城東高校の前を通ってみてください。正門奥に真新しい建物ができました。新しい自動車実習棟です。建物も新しくなるのにともない、学科名もモビリティ工業科と変更しました。もちろん自動車整備が中心になります。見学希望者はいつでもどうぞ。